27日に政府が東京電力管内で節電を呼びかける「電力需給逼迫(ひっぱく)注意報」を発令したのは、6月として記録的猛暑が続く中、企業などの活動が再開され需要が増加する週明けも重なり、供給力が追い付かなくなる可能性が生じたためだ。電力の需給バランスは、発電設備の稼働状況だけでなく、天候や時間帯でも大きく変化する。脱炭素化などを背景に夏と冬の電力不足傾向が常態化する中、電力需給の綱渡り状況は今後も続きそうだ。
電力を安定的に供給するには、需要に対して3%の供給予備率が必要とされる。経産省は26日時点で、27日に最も需給が逼迫するのは午後4時半から午後5時で、予備率は3・7%と予測。この時間帯以外も日中は7%台の水準が続くことから、注意報の発令に踏み切った。
しかし、実際の気温は前日の予想よりも0・5度程度上回った。そこに、雲が多かったことで太陽光発電の稼働率が想定の85%程度に低下した。気温が1度上昇すれば、需要が増加して予備率は2~3%下がるといわれており、27日午後4時半以降の予備率予測も、午前11時時点で1・2%まで低下した。
東電によると、予備率が3%を下回ったとしてもすぐに管内で停電などが発生するわけではない。ただ、需給のバランスが逆転すれば発電設備が故障し、大規模な停電につながるリスクがある。そのため、このまま需要が増え続けて予備率が0%に迫れば、需要を緊急的に遮断する「周波数低下リレー(UFR)」という装置が自動的に作動し、送配電網の一部で強制的に停電を起こす可能性はあるという。
一方、需給をコントロールできるうちは管内の広い範囲が停電する「ブラックアウト」となる可能性は低いという。ただ、発電設備で予期せぬトラブルなどが発生すれば、そのリスクも皆無ではない。平成30年に北海道で発生したブラックアウトも、地震に伴う主力の火力発電所の運転停止が原因だった。
経産省は停電リスクの低減のため、さらに需給状況が悪化することになれば「警報」に切り替えて、節電目標を設定するなど、より強い形で節電の要請を行う方針だ。
福島第一原発事故以降、原子力発電の稼働率が下がる一方で、脱炭素化の流れに伴い、火力発電所の休廃止が進む。天候に左右されやすい太陽光発電など再生可能エネルギーへの依存度が相対的に高まっていることも、需給バランスを保つことを難しくさせている。電力需給が最も厳しくなるタイミングが夕方となっているのも、太陽光発電の発電量が落ちていく時間帯と重なるためだ。
ロシアによるウクライナ侵攻で、エネルギー安全保障への関心が高まっている。電力需給の逼迫に直面する中、日本のエネルギー政策について改めて検証が求められそうだ。(蕎麦谷里志)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/HMJ34ACAIBOFPJMKPNHXZKIQSE.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/UFRRRC2DHVHALDUPZQ7XIGXXJY.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/G6PFYEKC6VCTVFRFS52SXCH4JY.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/NQNBOEYC2JFYPMYIBTIV2EZFII.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/JKBWT4KN4RBOHFK3S3HATWF3MI.jpg)

/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/PIYZ43PFMNBYFFBR5JZPPT2KB4.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/LEONAUNP5NABNDJEMHVISZFQ3U.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/AMM3KK2Y4VG7FIVNPYRAW5OY4E.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/QDFA7R7NHBBRZCBR6WE77LUG3E.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/CAI25EI3VJDRVEGRDY6M5M4FQQ.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/QAOBBVDWRZDQ7NHRBLHMFQBGHM.JPG)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/T3UCGCUXMRAVDDW33UUUWJF2MQ.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/7S4WTTGXKFDEPIBZPY23PTHETU.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/G6PFYEKC6VCTVFRFS52SXCH4JY.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/NQNBOEYC2JFYPMYIBTIV2EZFII.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/JKBWT4KN4RBOHFK3S3HATWF3MI.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/PIYZ43PFMNBYFFBR5JZPPT2KB4.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/LEONAUNP5NABNDJEMHVISZFQ3U.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/AMM3KK2Y4VG7FIVNPYRAW5OY4E.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/QDFA7R7NHBBRZCBR6WE77LUG3E.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/CAI25EI3VJDRVEGRDY6M5M4FQQ.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/QAOBBVDWRZDQ7NHRBLHMFQBGHM.JPG)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/T3UCGCUXMRAVDDW33UUUWJF2MQ.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/7S4WTTGXKFDEPIBZPY23PTHETU.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/7NE3V3S4BNGXZD6ZH7F454SGT4.PNG)
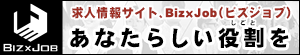


/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/PBT2JCCCJJIQ5KFHUKI6IVGC6I.jpg)

/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/DAYJD5WB6NBVVA2ZIZ6IQYKUOQ.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/OGPFIXNT4FA3TOZ5VH27AGG5L4.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/SDOUOIDHRJFDBJQU7F4EB7AEQE.jpg)
:quality(70)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/HUAUL5IO6BDDHJQSIHBNCKHVI4.JPG)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/TZXWVEN3LNAZXHPOT7CIPP7LJU.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/5RQNZZ4F5FBHHJWTAJG3UEYOL4.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/WJTYPHSX5BFYFKOJ5ZZQFBIOEU.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/SUQ4IH3BWFEYTGWQGH26BTFJJ4.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/ZIYR34BAZJB2JMX37U6I36XNXA.jpg)
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/Q5SNUGIZVRLX3BJR3QJMWYI2B4.jpg)