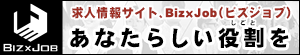生産者がオンラインの動画で商品を販売する「ライブコマース」が広まりつつある。利用者はコミュニケーションを取りながら商品を購入できるため安心感があり、新型コロナウイルス禍の新たな直販スタイルとして定着する可能性が高い。海外では東南アジアを中心に活用されており、日本国内でも地方の農産物や食材の販売に導入する動きが出始めている。
ライブコマースは、EC(電子商取引)サイトとライブ配信を融合した新しいオンライン販売の手法で、コメント機能もあるため販売側は実店舗に近い接客が可能になる。利用者は視聴中に気に入った商品があれば、ECを介して購入できる仕組みだ。
例えば生産者は農作物を収穫する畑や海産物を水揚げする漁港からライブ配信し食材を解説。利用者は質問することができるので、あたかも直売所で購入しているような臨場感が味わえる。売り手と買い手の新たな出会いが商品の拡販につながると期待されている。
ウェブサイト制作などを手掛けるヘノブファクトリー(東京都豊島区)は、売り手と買い手の接点拡大に着目。コロナ禍で収入が減った地方の生産者を盛り上げようと、令和2年に通販モール「全国津々浦々ライブコマース(つつうら)」の試験運用を始めた。
当初は15の生産者が200点の商品を出品してスタート。それがコロナ禍でインターネット通販の利用が増えるにつれて認知度も高まり、現在は生産者が約40に増加した。商品は500点以上で、6月には1000点以上に拡大し、本格運用へと移行する。
3月には東京都豊島区に出店する生産者の商品を集めた実店舗「お取り寄せスーパー つつうら」を開設。通信設備も設置し、生産者が「スタジオとして活用できるようにした」(谷脇しのぶ会長)という。
地方のホテルを発信拠点にライブコマースを始める動きもある。長崎県雲仙市にある老舗温泉ホテル「雲仙 有明ホテル」を同市内で運営する平湯リゾートは、7月をめどに通販モール「雲仙まるごとライブコマース」を開始する。
ライブコマースをスマートフォンで利用できるアプリ「POPO」を開発したポポホールディングス(東京都渋谷区)と協業し、ホテルから地元の食材や食品、観光サービスなどを発信、販売していく。平湯リゾートの担当者は「宿泊客が落ち込むホテルはもちろん、飲食店の営業自粛で売り上げが減少した雲仙の生産者を再生したい」と意気込む。
日本では始まったばかりのライブコマースだが、海外でも特に東南アジアでは急速に普及している。IT企業のトランスコスモスがアジア10都市を対象に昨年実施したライブコマースでの購入や認知度に関する調査によると、「購入したことがある」との回答が日本では5.9%だったのに対し、上海(中国)は49.1%、バンコク(タイ)は60.6%、ハノイ(ベトナム)では62.5%と軒並み高い。
日本は食の安全・安心に対する関心が比較的高いとされる。生産者の顔が見えるのが利点のライブコマースが浸透する下地は十分にある。(青山博美)