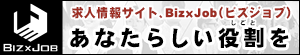新型コロナウイルス禍でテレワークが進み、コミュニケーション不足による弊害を指摘する声が強まっている。意思疎通が不十分でトラブル対応が遅れたり、業務の進捗(しんちょく)が把握しにくかったりといったマネジメント上の課題が顕在化しているためだ。とりわけ中小企業は深刻で、セミナーを手掛ける研修会社や健康支援サービスを手掛けるベンチャー企業などが従業員間のコミュニケーションを高める取り組みを始めている。
民間調査会社の帝国データバンク(東京都港区)が2月上旬に実施したアンケートによると、テレワークを取り入れている企業のうち、「メリットの方が多い」と答えたのは15.1%。「デメリットの方が多い」との回答は16.4%で、「メリット」を上回った。デメリットが多いとした企業の26.6%は「社内コミュニケーションが減少し、意思疎通が困難」という点を指摘した。アンケートはIT環境が充実した大企業も含まれているが、中小企業だけで見た場合、「デメリット」の回答が増えるとみられる。
こうした中、中小企業向け研修会社「セールスの学校」(同品川区)は、意思疎通を円滑にするため、上司参加型の新入社員向け研修に取り組む。
仕事の評価は結果に左右されるが、実際の業務ではプロセス(過程)も重要になる。セールスの学校はこのプロセスに着目。プロセスをより正確に把握するためには仕事の目標設定からの管理が必要で、上司とのコミュニケーションが必須になるためだ。
研修ではプロセスを管理するための手法「PDCA(Plan=計画、Do=実行、Check=評価、Action=改善)」を用いる。浅井隆志代表取締役は「コミュニケーションを重視した業務支援事業会社を目指す」という考えで、PDCAに力を入れるため4月に社名を「PDCAの学校」に変更する。
一方、企業の従業員にストレスチェックサービスなどを提供するベンチャー企業、ラフール(同中央区)は、スマートフォンを使って意思疎通を円滑にするサービスを提供する。
同社は平成31年にメンタルヘルス関連のデータを分析し専門家の知見も取り入れて提供する健康分析・サポートサービス「ラフールサーベイ」を開始。初期費用は10万円、月額利用料1人400円という低額料金が受け入れられ、現在1000社12万5000人が利用している。このサービスに、令和3年12月から組織内のコミュニケーションを高める新機能「感謝のキモチ」を追加した。従業員間でメッセージや簡単なスタンプを送ることで感謝や称賛を伝え合ったり、公私にわたる相談ができたりする場として活用できるようにした。
結木啓太社長は「従業員同士の激励や称賛、感謝の機会をつくることで、業務に対する意欲は向上する。従業員間の信頼関係も強まり、人間関係に起因する離職者減少にもつながる」と話す。
新型コロナ禍でテレワークが本格的に運用されて約2年がたつ。改めてコミュニケーション不足が業務上の課題として浮き彫りになっており、主にIT環境が脆弱(ぜいじゃく)な中小企業を対象に解消に向けた取り組みが活発化している。(青山博美)