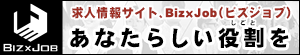厚生労働省は9日、医療機関のサービスの対価である診療報酬について、令和4年度の改定内容を決めた。新型コロナウイルスなどの感染症に対応できる医療体制の強化に向け、新たな加算の仕組みを設けたのが特徴だ。また、不妊治療の公的医療保険適用を体外受精などに拡大した。政府はこれを少子化対策に位置付けている。
中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)は9日、改定案を答申した。
感染症関連ではオミクロン株が広がるコロナ禍を踏まえ、平時から外来診療時の感染防止対策を行っている診療所に対し、患者1人当たり月1回60円を加算する「外来感染対策向上加算」を新設した。院内感染対策の責任者の設置や、大病院が行う感染症対策訓練への参加、感染症発生時に発熱外来の設置が可能であることをホームページで公表することなどが条件だ。
コロナ禍で診療所は、職員が少なく、十分な感染対策を取るのが困難だとして、コロナ患者を受け入れないケースが相次いだ。病床が逼迫(ひっぱく)した一因と指摘されている。同加算は患者受け入れ体制の確立に向け、診療所を政策的に誘導する狙いがある。
今回の改定でオンライン診療の在り方も変わる。コロナ対応で特例的に初診を解禁していたが、恒久措置とし、初診料を2140円から2510円に増やす。
不妊治療の保険適用拡大では、体外受精と顕微授精は子供1人につき、治療開始時に女性が40歳未満なら6回まで、40歳以上43歳未満は3回までを条件とする。人工授精は1万8200円、体外受精管理料は4万2000円などとした。体外受精は従来、1回平均約50万円かかっていた。
診療報酬は患者が窓口で原則1~3割を負担し、残りを保険料や税金で賄う。