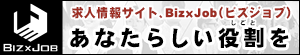新型コロナウイルスの感染が再拡大する中で、政府や東京都が産業界に対し、事業継続計画(BCP)の策定を求めた。多くの従業員が感染して事業の継続が困難になれば社会・経済活動が維持できなくなるからだ。
すでに鉄道大手や電力・通信などの公益サービスを手掛ける企業では、人員派遣や交代シフトの柔軟化などの新型コロナ対策を進めている。そうした取り組みを、今後は幅広い生活関連産業などにまで広げていきたい。
感染防止ではテレワーク(在宅勤務)の徹底も不可欠だが、中小企業などでは遅れが目立つ。特に大手企業は、下請けなどの取引先企業に対してテレワークを働きかける必要がある。
小池百合子東京都知事は主要な経済団体に対し、感染の急拡大で1割超の従業員が欠勤した場合でも、事業を継続できる計画の策定を要請した。山際大志郎経済再生担当相も経済界にテレワークの徹底などを求めた。
社会・経済活動の逼迫(ひっぱく)を招かないようにするには、産業界の協力が不可欠だ。とりわけ代替要員などをあらかじめ確保しておくBCPの策定は喫緊の課題である。そうした計画は台風や地震などの自然災害の発生時にも活用できる。非常時でも安定的に事業を運営できる体制の整備を急ぎたい。
大手鉄道会社では、乗務員らが感染して運行に支障が生じる恐れがあれば、近隣地区から応援要員を派遣する体制などを整えている。経営規模が小さな業界では他社に応援を要請するなど業界横断での協力を進めるべきだ。
テレワークをめぐっては、都内に本社を置く大手企業などで広がりを見せている。都の調査では、昨年11月時点で従業員300人以上の企業ではテレワークの実施が8割超にのぼるが、30~99人では半分程度にとどまる。中小・零細企業での推進が課題だ。
このため、都では従業員の7割以上が週3日テレワークすれば、通信費用などを支援する制度を始めた。テレワークは働き方改革にも資する。こうした制度を全国規模に広げていきたい。
社会・経済活動の維持には、濃厚接触者の待機日数の見直しも欠かせない。政府は14日間から10日間に変更した。オミクロン株の特性を見極めつつ、さらなる短縮を検討する柔軟さも必要だ。